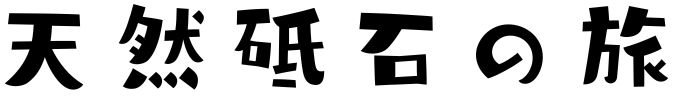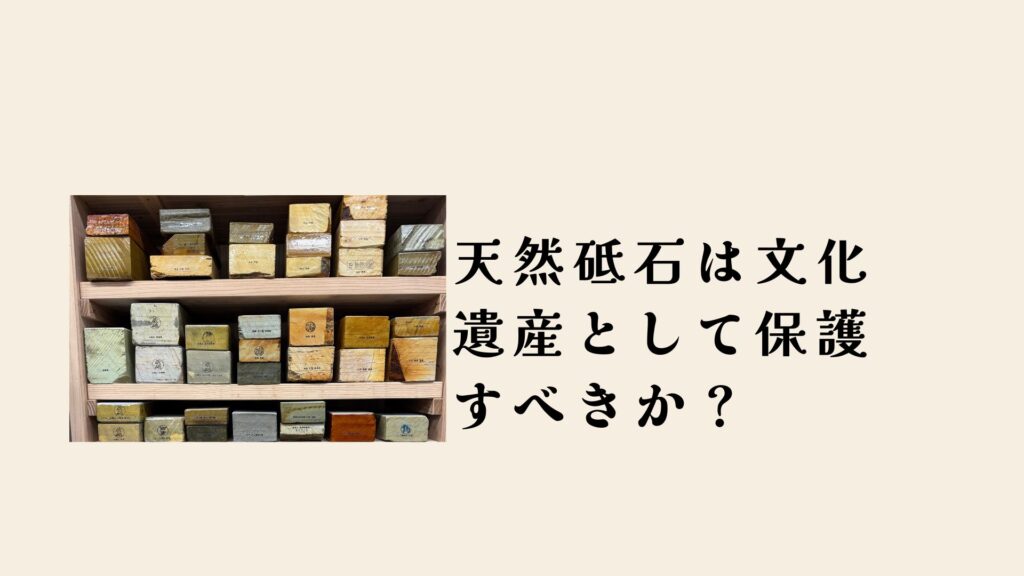
日本の伝統文化は、祭りや芸能といった華やかな側面だけでなく、日々の生活と深く結びついた道具や技術の中にも根付いています。その代表格のひとつが「天然砥石」です。刀剣や包丁を研ぎ澄ませるこの道具は、単なる石のかたまりではなく、長い歴史と職人の感性、美意識を内包した文化財とも言える存在です。
しかし近年、天然砥石は存続の危機に直面しています。その背景には、資源の枯渇、人造砥石の隆盛、そして現代社会の「効率」偏重の価値観があります。本稿では、天然砥石という素材と文化に焦点を当て、現代におけるその意義と存続の可能性を探っていきます。
資源としての天然砥石:枯渇する伝統
天然砥石は、長い地質時代をかけて形成された粘板岩や珪質岩の一種です。京都の中山、大突、奥殿などに代表される採掘地はすでにほとんどが閉山し、現在市場に流通している天然砥石の多くは、過去に掘り出され保管されていた在庫、または個人蔵からの放出品です。
特に京都・鳴滝地域に位置する中山鉱山は、明治期から昭和中期にかけて最盛期を迎えました。採掘は主に手掘りで、山の斜面に張り付くような作業環境のなか、職人たちは一日中ツルハシとノミで地層を追い続けたといいます。地権や採掘権の問題もあり、バブル期以降は休山が続き、現在では採掘された砥石の在庫が市場に出回る程度となっています。
文化庁の「伝統的工芸品産業の振興に関する基礎資料(2020年版)」でも、鉱山系の伝統産業における資源枯渇の問題は深刻であり、再採掘が物理的・経済的に困難であると指摘されています(※1)。
人造砥石の進化と文化的淘汰
天然砥石の役割は、すでに人造砥石によってほとんどの領域で代替可能になっています。とくに包丁の荒研ぎや中研ぎにおいては、セラミックやダイヤモンド砥石の高性能・均質性が重宝され、家庭用としても価格・入手性ともに人工砥石が主流となりました。
これは化学肥料の例にも似ています。1900年代初頭、ドイツの化学者フリッツ・ハーバーが空気中の窒素を固定する技術(ハーバー・ボッシュ法)を確立すると、それまで有機肥料に頼っていた農業は一気に化学肥料中心へと変化しました。技術革新が文化や風習を塗り替えていった典型です。
レコードからCD、CDからストリーミングへというメディアの変遷も同様です。利便性と再現性に優れる技術が旧来の文化を淘汰していくのは、ある意味で「自然な流れ」とも言えるでしょう。
守るべき伝統とは何か──不易流行の視点から

では、天然砥石は「守るべき伝統」なのでしょうか?
俳人・松尾芭蕉の提唱した「不易流行」という思想は示唆に富みます。「不易」は変わらぬ本質、「流行」はその時代に応じた変化。芭蕉はこの両方を両立させるべきだと説きました。
天然砥石をこの視点で見れば、道具としての役割(刃物を研ぐ)という機能は人造砥石で代替可能であり、「流行」によって変化してよい領域かもしれません。しかし、研ぎ味や研ぎ音、刃先に宿るわずかな違いなど、道具を通じて職人や料理人が感じる「微細な差異」は、まさに「不易」としての美意識の表れです。
人造砥石で研げる時代に、なぜ天然砥石なのか
ロマンだから。で終わるわけにもいかないので・・・
実際、包丁の刃をつけるだけならば、人造砥石で十分です。特に荒砥から中砥までの工程は、むしろ人造砥石のほうが効率的ですらあります。しかし、「仕上げ砥」の領域においては、いまだ天然砥石に軍配が上がるケースが多く存在します。
その理由の一つが、「砥石の個性」です。 天然砥石は、その産地や地層、採掘位置によって粒度や硬さが微妙に異なり、それが研ぎ味や刃の肌に多様な仕上がりを生み出します。これは人工砥石のような均一性のなかでは得難い表現です。
また、天然砥石で仕上げた包丁は、切れ味だけでなく、食材の細胞を壊さずに断ち切ることができるため、刺身などでは見た目の艶や味わいにも違いが出るという研究結果もあります(※2)。
切れる包丁は、味を変えるか?
科学的な観点からも、切れ味は味に影響します。2018年、味の素社の研究チームが行った研究では、切れ味の異なる包丁で切ったトマトや魚で、食味センサーによる味覚分析を行った結果、「うま味」や「酸味」にわずかながら差が出ることが確認されました(※3)。
これは、切断による細胞破壊の程度が異なることで、旨味成分の流出量が変わるためとされています。つまり、天然砥石で仕上げた高精度な刃は、単に料理の「見た目」だけでなく「味」にまで影響を及ぼしうるのです。
天然砥石の海外評価と価格動向
近年、海外でも日本産の天然砥石に対する評価が高まり、特に欧米や中国のプロ料理人・ナイフコレクターの間では人気が急上昇しています。京都・中山産や大突産の仕上げ砥は、eBayや専門オークションでは数十万円を超える価格で取引されることも珍しくありません。
中には「中山白巣板」「奥殿巣板」といったラベルのついた砥石が、ビンテージの日本刀と同様に“工芸的投資対象”として扱われている例すらあります。この背景には、砥石そのものの希少性に加え、日本独自の刃物文化に対する国際的関心の高まりも一因と考えられます。
保存か、活用か──制度としての文化財と支援
天然砥石を文化として残すべきという主張は、近年徐々に制度的な動きにもつながりつつあります。例えば、文化庁では「無形文化財」だけでなく、それを支える「用具・素材」や「生産技術」自体を支援対象に含める検討が進められています。
2021年には、京都のある砥石業者が文化庁の「地域文化資源活用事業」に採択され、採掘跡地の記録化や職人の聞き書きを通じたデジタルアーカイブ化が進行しました。さらに、地方自治体がクラウドファンディングを通じて、砥石山の保全活動を行った事例も存在します。
このように、「保存」だけでなく「活用」も視野に入れた柔軟な制度設計が、伝統技術の未来を左右する時代に入っているのです。
おわりに──税金を使ってでも残すべきか?
では、こうした天然砥石を「税金で守るべきか?」という問いに戻りましょう。
個人的には、税金を使ってまで天然砥石を残すことには懐疑的です。これは、私自身が小さな政府を志向するリバータリアン的な思想に親しんでいることも関係しています。天然砥石に限らず、「国にとって重要な文化財とは何か」を決める仕組みは、しばしば政治的な影響力に左右されやすく、結果として利権や既得権益の温床となりがちです。
初めは善意で始まった文化保護活動も、やがてはそれを担う組織の維持自体が目的化し、官僚的な自己目的化に陥るケースを幾度となく見てきました。
だからこそ、天然砥石に価値を見出す人々による、小規模でも実質の伴った自発的支援と知恵の集積こそが、本質的な保全につながると考えています。
出典・参考文献:
- ※1:文化庁『伝統的工芸品産業の振興に関する基礎資料(令和2年版)』
- ※2:『日本料理の包丁と味わいの関係性』(和食文化学会紀要 第8号、2021年)
- ※3:味の素株式会社 研究開発センター 『食味評価における刃物の切れ味の影響』(2018年、社内報告書要旨)