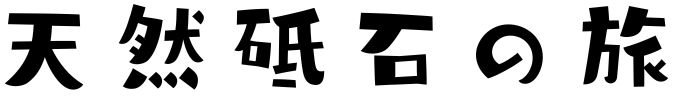1.中山とはどこにある?どんな地形?
中山砥石──それは、天然砥石の世界では知らぬ者のない伝説の存在。中でも“中山の戸前、浅葱、巣板”や“車口砥石”などは、研ぎの最終仕上げにおける最高峰とされ、希少価値・性能ともに群を抜いています。では、その中山とは、一体どんな場所なのでしょうか?
「中山」とは、京都市右京区の奥、三尾(さんび)エリアの北西に位置する一帯の通称です。地図上では「中山町」や「中山石山」などの地名が確認でき、嵯峨野から少し山を分け入ったあたりに広がっています。標高はおよそ200〜300メートル程度で、一般的な“山”というよりも「丘陵」あるいは「山背」といったほうが近い地形です。
実際に訪れると、登山靴も不要な程度の山道が続き、今では住宅街の背後にひっそりと佇む自然林。その“地味さ”からは、とても日本を代表する天然砥石が採れるとは想像もつきません。
2.中山の地質と砥石層の秘密
では、なぜこの中山という“目立たない丘”が、世界最高級の砥石を産出してきたのでしょうか?
理由はその地下に眠る特殊な地層にあります。
中山の地層は、「本口成り(ほんくちなり)」と呼ばれる、深海の泥が長い年月をかけて圧縮・変成された粘板岩層です。ここには放散虫(Radiolaria)という、極小のシリカ質プランクトンの化石が豊富に含まれており、それが天然の超微粒子研磨材として機能しています。
また、中山の粘板岩は「低〜中程度の変成作用」を受けており、チャートのように硬すぎず、泥岩のように柔らかすぎず、砥石として理想的な“割れやすく研げる”構造を保持。さらに自然風化によって表面に微細な粒子が浮き上がりやすくなっているため、抜群の滑走感と仕上がりを実現しています。
特筆すべきは、層ごとの個性の豊かさ。中山には「巣板」「戸前」「八枚」「天井巣板」「車口巣板」など、研ぎ味・硬度・見た目が異なる多数の層が重なっており、採掘された場所と深さによってまるで別の石かのように異なる表情を見せるのです。
3.採掘の歴史と現地の様子
中山での砥石採掘の歴史は、鎌倉時代にはじまり刀剣研磨としてスタートしました。特に江戸時代末期にはじまり、明治〜昭和初期にかけて全盛期を迎えます。とくに明治20年代以降は、大阪や東京の包丁鍛冶・刃物商人たちが競って買い付けに訪れたとされ、砥石山には常に採石の音が響いていたといいます。
採掘方法は主に露天掘り・水平坑道・垂直坑道(縦坑)の3種類。
- 比較的浅い巣板層などは露天掘り(斜面を階段状に削る)
- 戸前などを狙う場合は、横坑(水平トンネル)を掘って地層を追う
- そして、幻の車口層などを狙うには、縦に10〜15mも掘り下げる井戸状の縦坑を用いていたといわれます
こうした掘削は、すべて“節理”(自然な割れ目)を頼りに、人の目と手で丁寧に行われていました。石の「音」や「色」「きらめき」から良層を見極めるという、まさに職人芸の世界です。
現在は、中山砥石の採掘は実質終了しており、山中には古い坑道や崩れかけた石段、わずかに砥石層が露出した跡などが残るのみ。とはいえ、地名としての「中山石山」は今も地図に残り、砥石ファンの巡礼地としてひそかに人気を集めています。
4.地味な地形が、世界に誇る砥石を生んだ理由
ここまでの話を聞いて、「あれ?じゃあなぜ、もっと高い山じゃなかったのか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
実は、中山が“山すぎなかった”ことが、砥石にとってプラスに働いた可能性があります。
- 標高が高すぎないため、地層が崩れずに保存されやすい
- 地熱や変成作用が強くなりすぎず、砥石に適した“中間の硬さ”を保てた
- 人の手で掘削しやすく、搬出にも都合が良かった
つまり、中山は地味な“裏山”のような存在でありながら、砥石にとっては理想的な地質と環境が整っていたというわけです。
まとめ
中山は、地形としては小高い丘にすぎません。
しかし、その地下に広がっていたのは、世界最高峰と称される砥石層の宝庫でした。
地質的には、本口成り粘板岩で構成され、放散虫を多く含み、ちょうどよい変成を受けて、滑らかでありながら研磨力を持つ、最高の天然砥石素材が眠っていました。
その上に、江戸〜昭和にかけての職人たちの目と手が加わり、いまや「幻」とまで呼ばれる中山砥石が誕生したのです。
小さな山から生まれた大きな価値──それが中山という場所の真実なのです。パワー(きんにくん風)